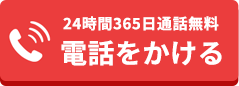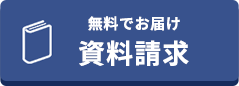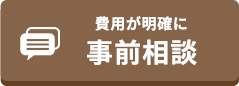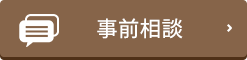はじめに
大切な人が亡くなったとき、最初に直面する大きな責任が「喪主」です。
「誰が務めるべき?」「何をすればいいの?」と戸惑う方も少なくありません。
本記事では、喪主の役割や段取り、葬儀前後の流れ、事前準備のポイントをわかりやすく解説します。
1. 喪主とは誰がなるべきか?決め方の基準
喪主とは、葬儀全体を代表し、準備・進行・参列者対応を担う責任者です。
一般的には以下の順序で務めることが多いです。
- 配偶者(夫または妻)
- 長男(または長女)
- その他の子ども(兄弟姉妹を含む)
- 近い親族(甥・姪など)
本人が生前に意思を示していた場合や、親族間の話し合いで決めることもあります。
2. 喪主の主な役割一覧
| タイミング | 喪主の役割 |
| 葬儀前 | 葬儀社との打ち合わせ、会場・形式の決定、訃報連絡、参列者リストの作成 |
| 通夜・葬儀中 | 参列者への挨拶、僧侶や司会者とのやり取り、焼香の先導、返礼品の確認 |
| 葬儀後 | 香典返しの手配、挨拶状の送付、法要準備、各種手続き対応、費用の精算 |
喪主は「表に立つ人」として、葬儀全体の調整・判断・責任を担う存在です。
3. 葬儀前・葬儀中・葬儀後の段取りと注意点
葬儀前にやること
- 葬儀社を決め、形式・日程・予算を打ち合わせ
- 遺影写真の準備、喪服の用意
- 親族・友人・職場などへの訃報連絡
※訃報の伝え方は、一般葬か家族葬かによって変わります。参列をお願いする場合、辞退をお願いする場合など、状況に応じた調整が必要です。
通夜・葬儀中にやること
- 葬儀社のリードに沿って式を進行
- 僧侶・司会者との対応
- 通夜や葬儀の締めでの挨拶
(例:「本日はお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございました」)
葬儀後にやること
- 香典返し(即日返しか後日配送かを決定)
- 初七日・四十九日など法要の準備
- 役所・年金・保険などの各種手続き
- 葬儀社や寺院への支払いなど費用精算
4. 喪主になったときに頼れるサポート・相談窓口
- 葬儀社の担当者:式の流れや物品の準備、進行など全体をサポート
- 親族・兄弟姉妹:受付・会計・返礼品担当など役割分担を
- 市区町村の窓口:死亡届、健康保険・年金関連の行政手続きを案内
- 専門家(行政書士・社労士・司法書士など):相続や名義変更など専門的な手続きの相談先
5. 喪主として後悔しないための事前準備
喪主は突然務めることになるケースが多いため、事前準備が安心につながります。
- 本人の意向(葬儀形式・宗教など)を聞いておく
- 家族間で「誰が喪主を務めるか」を話し合っておく
- 葬儀社を比較し、事前に見積もりや相談をしておく
- エンディングノートに希望をまとめておく
まとめ|喪主とは、遺族を代表して故人を送る存在
| 喪主の責任 | 内容 |
| 代表者としての判断 | 式の方針や参列対応を決定する |
| 参列者対応 | 挨拶、僧侶・葬儀社とのやり取り |
| 実務の調整 | 会場・時間・予算管理、精算処理 |
| 精神的な支柱 | 家族を支え、中心となって見送る |
喪主は一人ですべてを抱え込む必要はありません。葬儀社や親族の協力を得ながら、
「形式よりも、故人をどう送りたいか」という気持ちを大切にすることが一番の心得です。
おわりに
喪主の役割は大きな責任ですが、同時に故人との最後の時間をつくる尊い役目でもあります。
新潟で葬儀や法要を検討されている方は、地域の風習に詳しい
にいがたお葬式
での相談もおすすめです。
事前準備から葬儀後のサポートまで地域に寄り添った対応が受けられるので、安心して大切な方をお見送りできます。