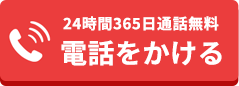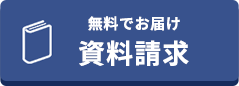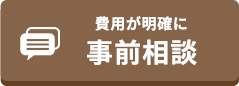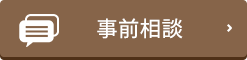増加する空き家
人口減少によって進む空き家の増加。家主が亡くなることで住む人がいなくなってしまうことも増加要因のひとつです。
総務省が2023年に行った調査では、全国の空き家数は900万戸を超え、前回の調査を行った2018年からわずか5年の間に50万戸以上も増えていることからも、誰にとってもとても身近な出来事だということがわかります。➡︎総務省令和5年住宅・土地統計調査
家主が亡くなることでご自宅が空き家となってしまうことで、大きく分けて「解体」と「相続」の2つの選択肢があります。
いずれも「後継者の負担にならないように」という気持ちから、生前準備できることです。
家は家族で暮らした思い出がいっぱい詰まったかけがえのない場所です。
生前準備としてまずはよく家族・親族間で話し合い、相続するのか解体するのか、もしくは売却をするのか方向性を決めましょう。
相続して活用する方法
家を財産として相続すると、後継者が活用できるというメリットがあります。
その際は「遺言書」にしっかりと記すのがおすすめです。遺書やエンディングノートには法的根拠がないことに留意しましょう。
後継者が複数人いる場合は遺産分割、相続する意思がないことを示す相続放棄といった方法もあります。
活用法には次のようなものがあります。
- 売却
築年数や立地条件、土地面積によっては資産価値が高くなるものもあります。
家の価値を客観的に知ることが大切です。
- 賃貸
売却せずとも貸し出すことで家賃収入が得られます。
資格、知識を有する専門業者に相談するのが安心です。
- 寄付
財産として活用する意思がない場合、寄付することで社会に貢献できるケースがあります。税制度などについても考慮して判断するとよいでしょう。
解体費用や業者は?
事業者が空き家の解体を行うには
- 建設業許可
- 解体工事業登録
この2つの許可と登録が必要となります。
個人で行う場合は不要ですが、建材にアスベストなどが含まれる時などは、自治体等への事前申告が必要です。
解体にかかる総工費が500万円以内であれば登録のみ、500万円を超える場合は建設業許可が必要となります。
近年、許可や登録がないまま受注し、トラブルの元となる業者も散見されますので、信頼のおける事業者への相談・依頼がカギです。
➡︎にいがたのお葬式 として連携する葬儀社では、遺品整理などの観点からも信頼のおける事業者と連携したサービスを提供しています。
費用イメージ
| 解体する建物の種類 | 1坪あたりにかかるおよその解体費用 | 建坪が約30坪の費用イメージ |
| 木造 | 2.5万円 〜 3.5万円 | 90万円 〜 150万円 |
| 鉄骨 | 3.5万円 〜 4.5万円 | 120万円 〜 180万円 |
| 鉄筋コンクリート | 4.5万円 〜 6万円 | 180万円 〜 240万円 |
「建物とは別にブロック塀やカーポートなどがある」「重機が使えない立地」「特殊な材料」など個別の事情で別途費用が加算されることがあります。
遺品や仏壇、神棚などは取り扱いに配慮が必要となりますので、葬儀社などへご相談ください。
「終活」のひとつとして
「私がいなくなった後は…」と、後継者の負担について考えるのは、ごく自然なことです。
家屋は財産のため、「生前贈与」をしておくと贈与税が非課税となるケースもあるため、家主の年齢や建物の状態、立地など把握して、家族の意思を揃えておきましょう。
空き家にまつわる手間やコスト、心配事をできるかぎり解消しようと、葬儀社では「宅地建物取引士」(宅建)の資格を有するスタッフにより、様々なサポートをはじめています。
家主が亡くなったことをきっかけに不要となった建物を買い取り、状態によりリノベーションを施した上で中古物件として売りに出したり、解体後の空き地を売りに出すことで、後継者の課税や維持管理コストを軽減しようという取り組みです。
仕事などの事情で実家を継げない/継がないという選択も増えていく時代です。生前からできることについて考え、相談しておくことも、安心へのアプローチですね。